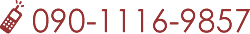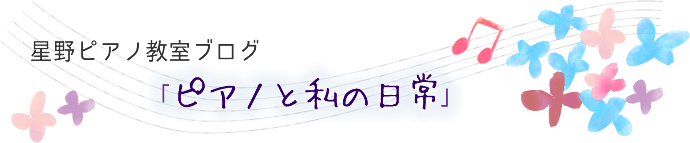未就学児でも入会から約2年で音大入試レベルの楽典を身に付ける指導法~というセミナーを受講してきました。
セミナーの題名を見ると、2年間で音大の過去問を解かせることが目的なのか?と思ってしまいますね。
楽典とは、音感、読譜、リズム、テクニック、曲を分析する力、楽語などのこと。曲を解釈するために必要なこと。
工夫とアイデアに富んだ独自の指導法で、これまで多くのコンクールで高い指導実績をあげてきた永瀬まゆみ先生のお嬢様が亡きお母さまの指導を受け継がれ今の時代により合った指導法に進化させ、コンクールに何人も生徒さんを輩出しているという実績を出されている内容でした。
永瀬先生は毎回のレッスンの中で小さな生徒さん(園児さん)でも10分間楽典の時間を入れ、その大切さと必要性を力説していました。高い演奏力にもつながっていくく理由のお話もとても共感を持てました。
2年間のカリキュラムの中で考えられた指導のレジュメを見せていただき、宿題の出し方、小さいな生徒さんへのアプローチの仕方などはとても参考になりました。
2時間でしたが、深い内容の学びでとても濃い充実した時間でした。無駄にならないよう…時間をかけても自分の中に落とし込んでいきたいです。そして、お教室の生徒さんへ還元していくことを目標に、頑張りたいです。
著名な先生方とご一緒させていただき、今回のセミナーを受講できた事に感謝でした。主催された先生方、永瀬先生、貴重なお話をありがとうございました 。
。